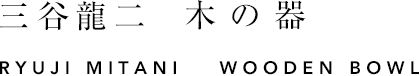読みもの
工芸にとって大切な4つのこと
食にまつわる器、道具は生活に密着しています。生活が変われば、ものも変わります。そのスピード感は年々早くなり、今使っているものが100年後に残っているかどうか予測するのは難しい。でも、ものだけでなく、その背景にある考え方を合わせれば100年生命を失わないものを見つけられるかもしれません。およそ100年前に柳宗悦が提唱した民芸が、今、人気なのも、ものはもちろん言葉が残ってきたからでしょう。
ものが残るには愛着が必要だと考えますが、デジタルアイテムは移り変わりも早く、愛着を持つ暇がありません。無機質なものが生活の中心に入ってくると、ある身体的な違和感を覚えます。その反動で、今の時代は、もう少し身体的に馴染みのいいものを無意識に欲しているのではないかとも感じます。そういう意味では、人間が存在する以上、デジタル化が進めば進むほど、工芸的なものは残っていくように思います。
愛着のある道具を身近に置くこと。直しながら長く使うこと。人とものとの関係を回復するためには「親密」であることが大切です。生活において身近で、よく使うものに包丁があります。何本か持っていますが、最近はこのタダフサの包丁ばかり使っています。大きさといい、切れ味といいちょうどいい。いい包丁というのは道具として優れているかどうか。僕は仕事で彫刻刀を使っていますが、切れる刃物とそうでないものでは作業性が全然違う。砥ぐのは少し面倒ですが、料理の仕上がりを見れば苦にはなりません。日々親密で、愛用の道具のひとつです。
現代の暮らしは人工的な構築物や形のないデジタルに囲まれ、人が本来持つ身体的な感覚は鈍くなっています。そうした中、工芸は「触覚の芸術」として再発見されているように思います。焼き締めの土肌、錆びた鉄、無垢の木は、どれも豊かな素材感覚に満ちています。ここで取り上げたホーローは、もともと工業製品として作られたものですが、金森さんはそれを工芸的な文脈で読み替えて、均質な仕上げでなく、鉄錆の部分やムラを残しています。工業製品ではマイナスとされていることを肯定し、その魅力を可視化する。これからはこの感覚が求められていくのではないでしょうか。
機械であれ、手仕事であれ、量産を繰り返していくうちに、「誰かの暮らしにつながっている」という感覚が摩滅していく気がします。それに変わるのが、利益の追求や機械のような無感覚。作る現場から、誰のために作っているのかが見えなくなってしまうと、もののリアリティも失われていきます。この湯沸かしは、燕市に200年続く槌起(ついき)銅器の技術で作られています。大橋さんは伝統の系譜を受け継ぎながらも、現代の暮らしや誰かの暮らしにつながることの大切さを考え、様々な人のデザインを取り込みながら銅器を制作しています。修行した工房では100年前に作られたやかんも現役でした。
植物が大地に根を下ろすように、ものにも根があり、栄養を吸収する大地があるように思います。植物という目に見える「図」にとって大地という「地」は欠かせません。道具という「図」にとっては、生活が「地」。ものと生活が離れてしまうと、養分が断ち切られ、生命力も減少するように思えてなりません。大谷さんの土鍋は、直火はもちろん、焼き菓子の型としてオーブンでも使えます。収納もしやすく、大変丈夫。使いやすさは使用頻度につながり、器と人の関係を近しくしてくれます。まさに「地」としての生活から養分を吸収し、そこから生まれた「器」なのです。
(2020/11 別冊太陽 掲載)
ものが残るには愛着が必要だと考えますが、デジタルアイテムは移り変わりも早く、愛着を持つ暇がありません。無機質なものが生活の中心に入ってくると、ある身体的な違和感を覚えます。その反動で、今の時代は、もう少し身体的に馴染みのいいものを無意識に欲しているのではないかとも感じます。そういう意味では、人間が存在する以上、デジタル化が進めば進むほど、工芸的なものは残っていくように思います。
タダフサの「包丁」
「親密」であること愛着のある道具を身近に置くこと。直しながら長く使うこと。人とものとの関係を回復するためには「親密」であることが大切です。生活において身近で、よく使うものに包丁があります。何本か持っていますが、最近はこのタダフサの包丁ばかり使っています。大きさといい、切れ味といいちょうどいい。いい包丁というのは道具として優れているかどうか。僕は仕事で彫刻刀を使っていますが、切れる刃物とそうでないものでは作業性が全然違う。砥ぐのは少し面倒ですが、料理の仕上がりを見れば苦にはなりません。日々親密で、愛用の道具のひとつです。

金森正起の「ホーローボウル」
素材感覚現代の暮らしは人工的な構築物や形のないデジタルに囲まれ、人が本来持つ身体的な感覚は鈍くなっています。そうした中、工芸は「触覚の芸術」として再発見されているように思います。焼き締めの土肌、錆びた鉄、無垢の木は、どれも豊かな素材感覚に満ちています。ここで取り上げたホーローは、もともと工業製品として作られたものですが、金森さんはそれを工芸的な文脈で読み替えて、均質な仕上げでなく、鉄錆の部分やムラを残しています。工業製品ではマイナスとされていることを肯定し、その魅力を可視化する。これからはこの感覚が求められていくのではないでしょうか。

大橋保隆の「湯沸かし」
「暮らし」につながっていること機械であれ、手仕事であれ、量産を繰り返していくうちに、「誰かの暮らしにつながっている」という感覚が摩滅していく気がします。それに変わるのが、利益の追求や機械のような無感覚。作る現場から、誰のために作っているのかが見えなくなってしまうと、もののリアリティも失われていきます。この湯沸かしは、燕市に200年続く槌起(ついき)銅器の技術で作られています。大橋さんは伝統の系譜を受け継ぎながらも、現代の暮らしや誰かの暮らしにつながることの大切さを考え、様々な人のデザインを取り込みながら銅器を制作しています。修行した工房では100年前に作られたやかんも現役でした。

大谷哲也の「白い土鍋」
「図」としてのもの、「地」としての生活植物が大地に根を下ろすように、ものにも根があり、栄養を吸収する大地があるように思います。植物という目に見える「図」にとって大地という「地」は欠かせません。道具という「図」にとっては、生活が「地」。ものと生活が離れてしまうと、養分が断ち切られ、生命力も減少するように思えてなりません。大谷さんの土鍋は、直火はもちろん、焼き菓子の型としてオーブンでも使えます。収納もしやすく、大変丈夫。使いやすさは使用頻度につながり、器と人の関係を近しくしてくれます。まさに「地」としての生活から養分を吸収し、そこから生まれた「器」なのです。
(2020/11 別冊太陽 掲載)