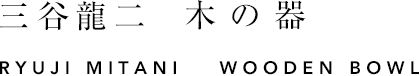読みもの
感知する力
見ているだけではすまなくて、つい手で触りたくなってくるものがあります。たとえば街を歩いていて、好きな型の車や、自転車なんかが道路際に置いてあったりすると、近づいて、手で撫でてしまいます。お店で、風合いのいい紙や、シルクや麻の手織の布などを前にしたら、もちろん見ているだけでは済みません。指でその感触や、張り具合などを確かめずにはいられません。
今年9月、住まいのある松本市内で「ハンスウエグナーとフィンユールの椅子展」という展覧会を僕たちで自主企画しました。椅子の持ち主から、古いものや使い込んだものあるので「座らないように」と、前もって言われていたものですから、会場では椅子を一段高い、平台に上げて展示しました。それでもチーク材で作られた流線型の美しいアーム(肘掛け)などを見ると、つい見ているだけでは済まなくなります。貼り紙を気にしながらも、手を伸ばして触る人がたくさんいました。食べ物のように口に触れるものから、衣服、食器、あるいは人が全体重をかけて上に乗る自転車や椅子。普段の生活の中で、直接からだに触れるものは、自分の体で覚えた心地よさを知っていますから、それを直接自分のからだで触れて確かめたくなるのも、無理はありません。 ものに触れる。つまり触覚は、昆虫などを見てもわかるように、本来は近づいてくる危険や、なにか害を与えるものに触れていることを、僕たちに知らせるためのものでした。かって、人が狩猟のために野を駆け回っていた頃、僕たちの五感はすべて、危険を感知するための探知機の役割を果たしていました。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚。これらすべてを最大限に発揮して、外界の様子を感じ取り、危険を素早く察知して、敵から自分たちの身を守ってきました。五感は、自分たちを取り巻くこの世を感じ取るための、極めて重要な感覚器官だったのです。現在では、身の回りの危険というのが大幅に減少したことで、この能力も発揮される機会が少なくなりました。五感は、快適さや、おいしさといった暮らしの場面で、主に働いているのです。
しかし、僕たちにしても、いつもただ快適さや、おいしさばかり求めているわけではありません。例えば、青年の頃、もっと差し迫った自分自身の問題を抱えながら、街を歩き回っていました。僕たちは、目的もなく、ただただ街を歩き回りながら、自分の生身の肌で、この世界を読みとろう、としていたように思います。それは、これまで学校や書物では決して知ることのできなかった、はじめて接するこの世の手触りを知るためでした。この世の中でこの先どうやって生きていくのだろう、と漠然とした不安や焦りを持ちながら、ヒリヒリするような皮膚感覚で、現実の手触りを感じ取ろうとしていました。それはちょうど狩をするために野を駆ける男たちのように、街を駆け抜けていたように思います。溢れる情報も、それまでの知識も手が届かない領域。その見えない世界に手をかざし、この世の手触りを感知することは、その当時も、そして今の僕たちの生命にとって、重要な力であることに、変わりはないはずです。
ものに触れる、といえば、ものづくりの人たちは毎日ものに触れて暮らしています。陶芸家は土。木工家は木。そして染め織りの人は糸。素材や、道具など、具体的なものに手を触れながら、それぞれの考え方を作り上げていきます。ものを作る人たちは、どちらかといえば、頭でなく、手でものを考える人たちなのです。この茶碗はちょっと重すぎる、それに中指があたる糸底の面が堅すぎて少し痛いとか、経験によって自分の体に覚え込ませたものの中から、自分の<好み>を探していきます。もちろん、作り手たちが触れるものは、仕事に関わるものばかりではありません。暮らしながら、いろんなものに触れているのです。たとえば、朝の布団の柔らかな手触り、鉄の欄干の冷たさ。崩れ落ちそうな土壁の粗い肌。山のせせらぎの透明な水.....。そうした様々な手触りの記憶を積み重ねた層の中から、長い時間をかけてそれこそ手探りで、自分自身に最も近いと感じる、かたちやテクスチャーを選び取っていくように思います。
現在は狩猟時代のように、生身の肉体を野の危険に晒すことはあまりありません。しかし、ものを作り出すということも、野に生身を晒し、ただ、自分の<感知する力>だけを頼りに、見えない領域に手探りで入り込んでゆく、という意味では、狩猟時代と変わりない大変さを持っているように思います。
だからこそ、身の回りの小さな手触りを丹念に拾い集めることと同時に、もっと大きな世界の手触りを感知する力を失わないこと。それは、いまもとても大切な能力だと思うのです。
今年9月、住まいのある松本市内で「ハンスウエグナーとフィンユールの椅子展」という展覧会を僕たちで自主企画しました。椅子の持ち主から、古いものや使い込んだものあるので「座らないように」と、前もって言われていたものですから、会場では椅子を一段高い、平台に上げて展示しました。それでもチーク材で作られた流線型の美しいアーム(肘掛け)などを見ると、つい見ているだけでは済まなくなります。貼り紙を気にしながらも、手を伸ばして触る人がたくさんいました。食べ物のように口に触れるものから、衣服、食器、あるいは人が全体重をかけて上に乗る自転車や椅子。普段の生活の中で、直接からだに触れるものは、自分の体で覚えた心地よさを知っていますから、それを直接自分のからだで触れて確かめたくなるのも、無理はありません。 ものに触れる。つまり触覚は、昆虫などを見てもわかるように、本来は近づいてくる危険や、なにか害を与えるものに触れていることを、僕たちに知らせるためのものでした。かって、人が狩猟のために野を駆け回っていた頃、僕たちの五感はすべて、危険を感知するための探知機の役割を果たしていました。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚。これらすべてを最大限に発揮して、外界の様子を感じ取り、危険を素早く察知して、敵から自分たちの身を守ってきました。五感は、自分たちを取り巻くこの世を感じ取るための、極めて重要な感覚器官だったのです。現在では、身の回りの危険というのが大幅に減少したことで、この能力も発揮される機会が少なくなりました。五感は、快適さや、おいしさといった暮らしの場面で、主に働いているのです。
しかし、僕たちにしても、いつもただ快適さや、おいしさばかり求めているわけではありません。例えば、青年の頃、もっと差し迫った自分自身の問題を抱えながら、街を歩き回っていました。僕たちは、目的もなく、ただただ街を歩き回りながら、自分の生身の肌で、この世界を読みとろう、としていたように思います。それは、これまで学校や書物では決して知ることのできなかった、はじめて接するこの世の手触りを知るためでした。この世の中でこの先どうやって生きていくのだろう、と漠然とした不安や焦りを持ちながら、ヒリヒリするような皮膚感覚で、現実の手触りを感じ取ろうとしていました。それはちょうど狩をするために野を駆ける男たちのように、街を駆け抜けていたように思います。溢れる情報も、それまでの知識も手が届かない領域。その見えない世界に手をかざし、この世の手触りを感知することは、その当時も、そして今の僕たちの生命にとって、重要な力であることに、変わりはないはずです。
ものに触れる、といえば、ものづくりの人たちは毎日ものに触れて暮らしています。陶芸家は土。木工家は木。そして染め織りの人は糸。素材や、道具など、具体的なものに手を触れながら、それぞれの考え方を作り上げていきます。ものを作る人たちは、どちらかといえば、頭でなく、手でものを考える人たちなのです。この茶碗はちょっと重すぎる、それに中指があたる糸底の面が堅すぎて少し痛いとか、経験によって自分の体に覚え込ませたものの中から、自分の<好み>を探していきます。もちろん、作り手たちが触れるものは、仕事に関わるものばかりではありません。暮らしながら、いろんなものに触れているのです。たとえば、朝の布団の柔らかな手触り、鉄の欄干の冷たさ。崩れ落ちそうな土壁の粗い肌。山のせせらぎの透明な水.....。そうした様々な手触りの記憶を積み重ねた層の中から、長い時間をかけてそれこそ手探りで、自分自身に最も近いと感じる、かたちやテクスチャーを選び取っていくように思います。
現在は狩猟時代のように、生身の肉体を野の危険に晒すことはあまりありません。しかし、ものを作り出すということも、野に生身を晒し、ただ、自分の<感知する力>だけを頼りに、見えない領域に手探りで入り込んでゆく、という意味では、狩猟時代と変わりない大変さを持っているように思います。
だからこそ、身の回りの小さな手触りを丹念に拾い集めることと同時に、もっと大きな世界の手触りを感知する力を失わないこと。それは、いまもとても大切な能力だと思うのです。