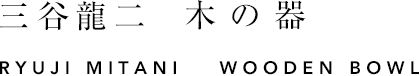読みもの
ちいさなものとこと
長い文:抽象的な写真と長い言葉
三谷龍二さんの作るものの魅力を伝えるのに言葉はいらないかもしれない。
それでもこうして言葉にしてみる機会を頂いたから、何となくつかんだ糸口をもう少し引き寄せてみたいと思う。つたない旅の記録に、ひとりでもふたりでもお付き合い下さる方がいれば嬉しい。
三谷さんの作るもののどんなところが好きなのだろう。
考えてみると、2010年の冬、鎌倉の神奈川県立近代美術館で開かれていた内藤礼さんの展覧会でみた、風になびく細いほそいリボンを思い出す。
内藤さんの作るものをとても工芸的だと感じた瞬間だ。
現代美術の枠組みでは、あらゆる方法や形態を用いた表現行為が出現し、美術・芸術の定義が大きく変わったように思える昨今でさえ、美術や芸術というのは作り手が主体となって何かを作り出す、表すものであるという考えは依然として根強いように思う。
しかしこの展示で、内藤さんの作るものは自分自身が主体となって何かを作り出し表しているというより、そこにある空間や自然にそっと手を添えて、うつくしいものへの向かって私たちの心が開かれるように導いているようであった。
内藤さんはリボンの細さと長さ、設置の仕方や場所を選ぶ。その時に細心の注意がはらわれるが、最後は風に任される。みるひとにゆだねられる。
内藤さんの作るものはどちらかといえば彼女のものというより、みる側、体験する側にある段階で渡され、贈られているようであり、それはささやくように繊細で、またささやかである。
2012年の秋、念願だった直島と豊島を訪れた。
ここでの経験は、三谷さんの作るものと内藤さんの作るものとの共通点を再び強く感じさせることになる。
中でも最も印象的だったのが、内藤礼さんと建築家・西沢立衛さんによる豊島美術館であった。
大きなきのこか水の粒みたいな形をした円形の建物の一部は大きくくり抜かれたように屋根がなく、空とつながっていて、雨が降れば水たまりができ、風が吹けば落ち葉が舞い降りた。
壁がそのまま湾曲して上に伸びたような屋根のおかげで、ところどころ光が遮られ、陰ができる。
建物の外と中の境は曖昧で、常に外を感じられる解放感と洞穴の中にいるような不思議な安心感とを同時に味わった。
包まれるように体中に自然のやさしい刺激を与えられ、少し五感が慣れた頃、ようやく地面から水の粒がぽこぽこと生まれては流れ、あちらこちらに水たまりを作っていることに気が付いた。
森の中でひとつのきのこに気が付くと、目が開かれ、一面茶色の落ち葉にみえていた地面の中に急に次々ときのこをみつけられるみたいに、あっちにもこっちにもと追いかけて行きたくなるようだった。
その水の粒は透明でまるく、みればみるほど、どんな宝石も敵うまいと思うほどうつくしかった。
風が吹くと、ころころと流れて隣の水の粒に混ざったり、ふるふると少し揺れながらとどまったり、いつまでみていても飽きない。
そこでは水の粒は抽象化され、背負わされている当たり前の定義からすっかり自由になっていた。水であるし、生き物のようでもあるし、初めてみるものみたいに新鮮で、名付けようのないただうつくしい何かであった。
抽象化された水の粒は普段知っている具体的な水の粒よりもっと自然に近いような気がした。例えば、空から降ってくる雨粒より、内藤さんによって考えられ、おそらく精密な設計のもと地面から生まれ出ている水の粒の方に、自然を強く感じた。
具体的なものだということは、よく知っているということで、それゆえひとはいつもの思考回路を使ってすんなり理解してしまう。ところが抽象的だということは具体的な、よく知っている情報が読み取りにくく、何だかわからない状態が続くため、思考回路につながるより先に五感の方が開かれる。理性ではなくて感性の方が優位に働く。何だかわからない混沌としながらも何か余地のある状態。それは自然そのものの姿であり、その状態にある時ひとは自然に近いと言えるのではないだろうか。
三谷さんのうつわはうつくしいだけでなく、とても使いやすい。現代の暮らしの中でどんな大きさや形、用途が求められているかが大変よく考えられているからである。
ボウルとかスプーンとか名前が付いていて、当然、食べ物を盛ったりすくったり出来る。こんなに具体的なのに、なぜか三谷さんのうつわを抽象的だと感じる。それはやはり、三谷さんのうつわに自然があるからではないかと思う。木そのものに手を加えた時点で、具体的な形、用途へ向かっていると同時に木そのものの形を失うことで、抽象化されてもいる。誰もが知っている具体的な木はまだ誰も知らない何かになっていく。木を削り出している途中の塊をごろんと目の前に置かれたら、何だろうと戸惑うだろうし、もしかしたら抽象的な彫刻作品かと思うかもしれない。そこにさらに手を加えて形が出来上がると何だかわからないものはうつわになる。うつわになるのだけれど、そこにひとかけらの余白のようなものが残される。
余白とは、コントロールし切らないこと。もしくはコントロールし切れないと知っていること。ひとの手が加わることで、余白=コントロールし切れないことを受ける側にかえって強く感じさせる。それが、人の手の加わったものの中に自然があると感じる理由でないかと思う。
風にリボンが揺れるみたいに自然に手を添えるようにして、あとはどうぞとゆだねること。
自然にゆだねられ、うつわも水の粒も常に変化していく。
私たちはゆだねられ、自由を知って、ささやかだけれど大きな幸福感を味わうことになるだろう。
三谷さんも内藤さんも、自己表現とは違って、日常の中にあるうつくしい瞬間、幸福なひとときへの入り口のようなものを用意してくれる。その入り口に、目立つような看板は立っていないし誰も大声でここだよと教えてはくれない。
日常はちいさなものに囲まれたちいさなことの繰り返し。だけれど、三谷さんのうつわにのせた焼きたてのパンのにおいに、たっぷり盛ったサラダと木肌の色にふと感じ入る。
言葉にしたらどこかへ消えていってしまいそうな、儚いけれど確かな幸福感。こんな時、テーブルにある三谷さんのうつわと見慣れた水の粒に心動かされた内藤さんの空間とがとても近く感じる。
ふと気が付けば、ちいさなものとことの中にこそ、たくさんの愛すべきかけらたちが静かに、でも確実に存在している。
私たちはいつだって歓迎されているのだから、肩の力をすっと抜いて、ちいさな入り口の扉を開ければいい。
短い文:いくつかの具体的なアイテムの写真と短い言葉
バット
空間を区切るということ。装置。それによっていつもの光景、知っているはずのものはまるで違ってみえる。
新鮮な空気を運んでくれる。
Thin Bowl
木の塊から深く薄く削り出される。ぽっかりと空いた空間の分だけ私たちには自由がやってくる。空間を埋める自由もあるし、そのままにしておく自由もある。
アイスクリームスプーン
その存在が愛らしい。木で出来ているのに花のよう。好きな花を一輪ずつ少しずつ集めるみたいに、スプーンのブーケを作ってみたい。
山本千夏
三谷龍二さんの作るものの魅力を伝えるのに言葉はいらないかもしれない。
それでもこうして言葉にしてみる機会を頂いたから、何となくつかんだ糸口をもう少し引き寄せてみたいと思う。つたない旅の記録に、ひとりでもふたりでもお付き合い下さる方がいれば嬉しい。
三谷さんの作るもののどんなところが好きなのだろう。
考えてみると、2010年の冬、鎌倉の神奈川県立近代美術館で開かれていた内藤礼さんの展覧会でみた、風になびく細いほそいリボンを思い出す。
内藤さんの作るものをとても工芸的だと感じた瞬間だ。
現代美術の枠組みでは、あらゆる方法や形態を用いた表現行為が出現し、美術・芸術の定義が大きく変わったように思える昨今でさえ、美術や芸術というのは作り手が主体となって何かを作り出す、表すものであるという考えは依然として根強いように思う。
しかしこの展示で、内藤さんの作るものは自分自身が主体となって何かを作り出し表しているというより、そこにある空間や自然にそっと手を添えて、うつくしいものへの向かって私たちの心が開かれるように導いているようであった。
内藤さんはリボンの細さと長さ、設置の仕方や場所を選ぶ。その時に細心の注意がはらわれるが、最後は風に任される。みるひとにゆだねられる。
内藤さんの作るものはどちらかといえば彼女のものというより、みる側、体験する側にある段階で渡され、贈られているようであり、それはささやくように繊細で、またささやかである。
2012年の秋、念願だった直島と豊島を訪れた。
ここでの経験は、三谷さんの作るものと内藤さんの作るものとの共通点を再び強く感じさせることになる。
中でも最も印象的だったのが、内藤礼さんと建築家・西沢立衛さんによる豊島美術館であった。
大きなきのこか水の粒みたいな形をした円形の建物の一部は大きくくり抜かれたように屋根がなく、空とつながっていて、雨が降れば水たまりができ、風が吹けば落ち葉が舞い降りた。
壁がそのまま湾曲して上に伸びたような屋根のおかげで、ところどころ光が遮られ、陰ができる。
建物の外と中の境は曖昧で、常に外を感じられる解放感と洞穴の中にいるような不思議な安心感とを同時に味わった。
包まれるように体中に自然のやさしい刺激を与えられ、少し五感が慣れた頃、ようやく地面から水の粒がぽこぽこと生まれては流れ、あちらこちらに水たまりを作っていることに気が付いた。
森の中でひとつのきのこに気が付くと、目が開かれ、一面茶色の落ち葉にみえていた地面の中に急に次々ときのこをみつけられるみたいに、あっちにもこっちにもと追いかけて行きたくなるようだった。
その水の粒は透明でまるく、みればみるほど、どんな宝石も敵うまいと思うほどうつくしかった。
風が吹くと、ころころと流れて隣の水の粒に混ざったり、ふるふると少し揺れながらとどまったり、いつまでみていても飽きない。
そこでは水の粒は抽象化され、背負わされている当たり前の定義からすっかり自由になっていた。水であるし、生き物のようでもあるし、初めてみるものみたいに新鮮で、名付けようのないただうつくしい何かであった。
抽象化された水の粒は普段知っている具体的な水の粒よりもっと自然に近いような気がした。例えば、空から降ってくる雨粒より、内藤さんによって考えられ、おそらく精密な設計のもと地面から生まれ出ている水の粒の方に、自然を強く感じた。
具体的なものだということは、よく知っているということで、それゆえひとはいつもの思考回路を使ってすんなり理解してしまう。ところが抽象的だということは具体的な、よく知っている情報が読み取りにくく、何だかわからない状態が続くため、思考回路につながるより先に五感の方が開かれる。理性ではなくて感性の方が優位に働く。何だかわからない混沌としながらも何か余地のある状態。それは自然そのものの姿であり、その状態にある時ひとは自然に近いと言えるのではないだろうか。
三谷さんのうつわはうつくしいだけでなく、とても使いやすい。現代の暮らしの中でどんな大きさや形、用途が求められているかが大変よく考えられているからである。
ボウルとかスプーンとか名前が付いていて、当然、食べ物を盛ったりすくったり出来る。こんなに具体的なのに、なぜか三谷さんのうつわを抽象的だと感じる。それはやはり、三谷さんのうつわに自然があるからではないかと思う。木そのものに手を加えた時点で、具体的な形、用途へ向かっていると同時に木そのものの形を失うことで、抽象化されてもいる。誰もが知っている具体的な木はまだ誰も知らない何かになっていく。木を削り出している途中の塊をごろんと目の前に置かれたら、何だろうと戸惑うだろうし、もしかしたら抽象的な彫刻作品かと思うかもしれない。そこにさらに手を加えて形が出来上がると何だかわからないものはうつわになる。うつわになるのだけれど、そこにひとかけらの余白のようなものが残される。
余白とは、コントロールし切らないこと。もしくはコントロールし切れないと知っていること。ひとの手が加わることで、余白=コントロールし切れないことを受ける側にかえって強く感じさせる。それが、人の手の加わったものの中に自然があると感じる理由でないかと思う。
風にリボンが揺れるみたいに自然に手を添えるようにして、あとはどうぞとゆだねること。
自然にゆだねられ、うつわも水の粒も常に変化していく。
私たちはゆだねられ、自由を知って、ささやかだけれど大きな幸福感を味わうことになるだろう。
三谷さんも内藤さんも、自己表現とは違って、日常の中にあるうつくしい瞬間、幸福なひとときへの入り口のようなものを用意してくれる。その入り口に、目立つような看板は立っていないし誰も大声でここだよと教えてはくれない。
日常はちいさなものに囲まれたちいさなことの繰り返し。だけれど、三谷さんのうつわにのせた焼きたてのパンのにおいに、たっぷり盛ったサラダと木肌の色にふと感じ入る。
言葉にしたらどこかへ消えていってしまいそうな、儚いけれど確かな幸福感。こんな時、テーブルにある三谷さんのうつわと見慣れた水の粒に心動かされた内藤さんの空間とがとても近く感じる。
ふと気が付けば、ちいさなものとことの中にこそ、たくさんの愛すべきかけらたちが静かに、でも確実に存在している。
私たちはいつだって歓迎されているのだから、肩の力をすっと抜いて、ちいさな入り口の扉を開ければいい。
短い文:いくつかの具体的なアイテムの写真と短い言葉
バット
空間を区切るということ。装置。それによっていつもの光景、知っているはずのものはまるで違ってみえる。
新鮮な空気を運んでくれる。
Thin Bowl
木の塊から深く薄く削り出される。ぽっかりと空いた空間の分だけ私たちには自由がやってくる。空間を埋める自由もあるし、そのままにしておく自由もある。
アイスクリームスプーン
その存在が愛らしい。木で出来ているのに花のよう。好きな花を一輪ずつ少しずつ集めるみたいに、スプーンのブーケを作ってみたい。
山本千夏