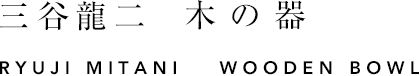読みもの
銀の匙、木の匙
三谷さんは、白色が好き。
そう本で読んだ。
白いもの。塩、雪、白樺、歯、骨、星、月、乳……。
たとえば、砂糖、小麦粉、米、紙、白磁。大切なものは、白いことが多い。最初から白いのではなくて、大事にしようとすると、結果的に、白くなってしまうものなのかもしれない。
善きものとして、昔の人たちがあえて白に祈りを込めていたことが、よくわかる。
世界のそこここで白は求められた。
たとえばそのように世界中、変わらないものがある。
その一つは、匙の形。
*
私は、三谷さんの作る道具を手に取ったことがない。写真でしか、みたことがない。
長らく小さな南の島で生活をしていたので、それらに出会う機会はことごとくなかった。
だけれど、三谷さんの本で読んで知ったことがある。
それは、『木の匙』から三谷さんの道具作りが始まったということ。
ではなぜ、木の匙からはじまったのだろうか。私はその答えについて考えを巡らせようと思う。
*
『銀の匙』という私小説がある。一九一二年、大正元年の長野県信州野尻湖畔でそれは書かれた。
三谷さんのアトリエにほど近い場所。物語はたんたんと、赤ん坊が青年になるまでの日常が描かれている。
赤ん坊の頃、叔母に銀の匙で薬を飲ませてもらったこと、木屑を口に入れた時の舌や頬が引き締まるような味、もう貴方とは遊ばないと友人に言われたこと、これが恋かもしれないと気づいた日、兄との決別、先生への抗議、恋に敗れ、飼っていた蚕の死、その死とともに、世の中の摂理のようなものを漠然と知る。誰もが経験したかのような、その過程。口に含んで何かを理解する、幼き日の記憶。
物語の中で、古い茶箪笥の引き出しから見つかった銀の匙。
英国では、富や能力に恵まれ、一生食べるに困らない人、という意味がある。
『Silver spoon』。
そういう祈りの道具。このことが幸福の象徴である、そんな時代があった。
刻は過ぎ、高度経済成長期も過ぎ、貧富の差が生まれた小さなこの亜細亜の島国は、湿度と人口が多く、比較的小さな体つきでも小さいと思えるアパルトマン、集合住宅にひしめいて、人々は暮らしていた。それでも暮らしていけるのは、核家族化が進んだ証拠。一つの部屋は一つの細胞。西洋化されたインテリア、最小単位の家族形態、共同体。
核家族の引き出しの中には、銀色の匙がきっと入っている。自宅で洋風の食べ物を食べることが日常だったから。
しかしほとんどの場合、『銀の』匙ではない。『銀色の』匙である。
そんな時代に三谷さんの木の匙は生まれた。
そうか、匙といえば西洋的なるものを連想しがちだけれど、銀の匙が生まれる前はどこの国でも、木の匙があった。
そして、その匙の形はおおよそ同じ形態をしている。重力と食物の特性の兼ね合い、手と口の構造。
人間。この惑星の上で変わらない条件たち。
木の匙、それは、銀が象徴するような富や権力に対してのやわらかな抵抗の形なのではないかと、私は思う。
(富は今もなお、幸福の象徴でありえるか)
その形状は普遍であり、原初的な素材であり、あらゆる人類の起源。
無国籍。ここではないどこか。白紙。はじまり。
*
私は、三谷さんの作る道具を手に取ったことがない。写真でしか、みたことがない。
長らく小さな南の島で生活をしていたので、それらに出会う機会はことごとくなかった。
だけど、実物をみて、いつか触りたいと願っていて、
ついにその日がやってくる。
潔白、告白、空白、白熱、白地図、白銀、白夜、白日‥‥。
白漆の塗られた三谷さんの木の器で、麗しい真白なお菓子を、私はきっと口に含んでみたいと思う。
そうして、言葉も持たないころの私になって、やわらかなこの世界のひみつに、そっと触れてみたい。
遠藤薫
そう本で読んだ。
白いもの。塩、雪、白樺、歯、骨、星、月、乳……。
たとえば、砂糖、小麦粉、米、紙、白磁。大切なものは、白いことが多い。最初から白いのではなくて、大事にしようとすると、結果的に、白くなってしまうものなのかもしれない。
善きものとして、昔の人たちがあえて白に祈りを込めていたことが、よくわかる。
世界のそこここで白は求められた。
たとえばそのように世界中、変わらないものがある。
その一つは、匙の形。
*
私は、三谷さんの作る道具を手に取ったことがない。写真でしか、みたことがない。
長らく小さな南の島で生活をしていたので、それらに出会う機会はことごとくなかった。
だけれど、三谷さんの本で読んで知ったことがある。
それは、『木の匙』から三谷さんの道具作りが始まったということ。
ではなぜ、木の匙からはじまったのだろうか。私はその答えについて考えを巡らせようと思う。
*
『銀の匙』という私小説がある。一九一二年、大正元年の長野県信州野尻湖畔でそれは書かれた。
三谷さんのアトリエにほど近い場所。物語はたんたんと、赤ん坊が青年になるまでの日常が描かれている。
赤ん坊の頃、叔母に銀の匙で薬を飲ませてもらったこと、木屑を口に入れた時の舌や頬が引き締まるような味、もう貴方とは遊ばないと友人に言われたこと、これが恋かもしれないと気づいた日、兄との決別、先生への抗議、恋に敗れ、飼っていた蚕の死、その死とともに、世の中の摂理のようなものを漠然と知る。誰もが経験したかのような、その過程。口に含んで何かを理解する、幼き日の記憶。
物語の中で、古い茶箪笥の引き出しから見つかった銀の匙。
英国では、富や能力に恵まれ、一生食べるに困らない人、という意味がある。
『Silver spoon』。
そういう祈りの道具。このことが幸福の象徴である、そんな時代があった。
刻は過ぎ、高度経済成長期も過ぎ、貧富の差が生まれた小さなこの亜細亜の島国は、湿度と人口が多く、比較的小さな体つきでも小さいと思えるアパルトマン、集合住宅にひしめいて、人々は暮らしていた。それでも暮らしていけるのは、核家族化が進んだ証拠。一つの部屋は一つの細胞。西洋化されたインテリア、最小単位の家族形態、共同体。
核家族の引き出しの中には、銀色の匙がきっと入っている。自宅で洋風の食べ物を食べることが日常だったから。
しかしほとんどの場合、『銀の』匙ではない。『銀色の』匙である。
そんな時代に三谷さんの木の匙は生まれた。
そうか、匙といえば西洋的なるものを連想しがちだけれど、銀の匙が生まれる前はどこの国でも、木の匙があった。
そして、その匙の形はおおよそ同じ形態をしている。重力と食物の特性の兼ね合い、手と口の構造。
人間。この惑星の上で変わらない条件たち。
木の匙、それは、銀が象徴するような富や権力に対してのやわらかな抵抗の形なのではないかと、私は思う。
(富は今もなお、幸福の象徴でありえるか)
その形状は普遍であり、原初的な素材であり、あらゆる人類の起源。
無国籍。ここではないどこか。白紙。はじまり。
*
私は、三谷さんの作る道具を手に取ったことがない。写真でしか、みたことがない。
長らく小さな南の島で生活をしていたので、それらに出会う機会はことごとくなかった。
だけど、実物をみて、いつか触りたいと願っていて、
ついにその日がやってくる。
潔白、告白、空白、白熱、白地図、白銀、白夜、白日‥‥。
白漆の塗られた三谷さんの木の器で、麗しい真白なお菓子を、私はきっと口に含んでみたいと思う。
そうして、言葉も持たないころの私になって、やわらかなこの世界のひみつに、そっと触れてみたい。
遠藤薫