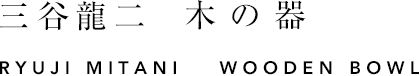読みもの
月夜のボタン
何かの役に立つわけではなく、人目をひく美しさもないが、人をその場から立ち去りがたい思いにさせるものがある。中原中也にとってそれは月夜の浜辺に落ちていたボタンであった。
月夜の晩に、ボタンが一つ/ 波打際に、落ちていた。
それを拾って、役立てようと/ 僕は思ったわけでもないが
なぜだかそれを捨てるに忍びず/ 僕はそれを、袂に入れた。
(中原中也「月夜の浜辺」)
人に見捨てられ、いまにも波に攫われそうなボタンは、月光のもとで何よりも無垢な存在として浜辺をさまよう詩人の琴線に触れた。このとき「指先に沁み、心に沁みた」のは、ボタンそのものというよりその佇まいだったのではないだろうか。
三谷さんの手になるPaper Blocksは、月夜のボタンのように、ひっそりとただそこに在るものの、どこか影を宿した佇まいを感じさせる。三谷さん自身が漆で紙を張り合わせて 形をつくり、彩色を施し、新たに制作したものであるにもかかわらず、その姿が古びた紙製の箱や積木にどこか似ているからだろうか。中身はとうに失われ、色が褪めてところどころ擦り切れた箱も、子どもが成長した後に押し入れの片隅に残された積木も、人々が関心を失い、存在すら忘れてしまったものである。三谷さんもまた人間のあらゆる欲望の対象から解放されたものが持つ無垢な佇まいに引かれ、その場を立ち去りがたく思う人の一人であるにちがいない。
だれの目にも見える姿や形、色や光とは違い、佇まいや影は捉えどころがない。みなが同じように感じるわけではなく、次の瞬間には失われているかもしれない。太陽であれ月であれ、ものに射す光ではなくものが宿す影に気づくかどうか、片隅で忘れられたものの佇まいに無垢を感じるかどうかはすべてその人次第である。
土田眞紀(同志社大学講師)
月夜の晩に、ボタンが一つ/ 波打際に、落ちていた。
それを拾って、役立てようと/ 僕は思ったわけでもないが
なぜだかそれを捨てるに忍びず/ 僕はそれを、袂に入れた。
(中原中也「月夜の浜辺」)
人に見捨てられ、いまにも波に攫われそうなボタンは、月光のもとで何よりも無垢な存在として浜辺をさまよう詩人の琴線に触れた。このとき「指先に沁み、心に沁みた」のは、ボタンそのものというよりその佇まいだったのではないだろうか。
三谷さんの手になるPaper Blocksは、月夜のボタンのように、ひっそりとただそこに在るものの、どこか影を宿した佇まいを感じさせる。三谷さん自身が漆で紙を張り合わせて 形をつくり、彩色を施し、新たに制作したものであるにもかかわらず、その姿が古びた紙製の箱や積木にどこか似ているからだろうか。中身はとうに失われ、色が褪めてところどころ擦り切れた箱も、子どもが成長した後に押し入れの片隅に残された積木も、人々が関心を失い、存在すら忘れてしまったものである。三谷さんもまた人間のあらゆる欲望の対象から解放されたものが持つ無垢な佇まいに引かれ、その場を立ち去りがたく思う人の一人であるにちがいない。
だれの目にも見える姿や形、色や光とは違い、佇まいや影は捉えどころがない。みなが同じように感じるわけではなく、次の瞬間には失われているかもしれない。太陽であれ月であれ、ものに射す光ではなくものが宿す影に気づくかどうか、片隅で忘れられたものの佇まいに無垢を感じるかどうかはすべてその人次第である。
土田眞紀(同志社大学講師)